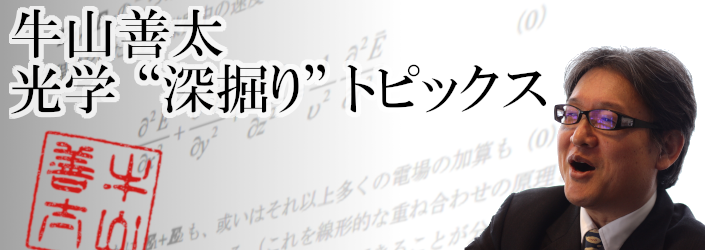前回では最小二乗法を、焦点距離を計算するという最も簡単な光学的な計算に用いた。そこでは焦点距離もバックフォーカスも同じように5mm 伸びるという都合の良い目標を立ててしまった。最小二乗法の基本的な動きを見ていただくためにそうした訳であるが、今回はより、実際的な方向に(それでも非常に単純でありますが)持っていきたいと思う。
osc-japan
【New】87. 最小二乗法について 4
今回はこれまでに取り上げさせていただいた最小二乗法を、光学的な計算に用いてみることにする。手始めに最も単純な焦点距離の計算にである。現状の単レンズを最小二乗法により所望の焦点距離を持つ様にする。勿論、特に単レンズであれば簡単に所望の焦点距離の曲率等はきん軸計算により得られてしまうが、ここでは敢えて最小二乗法により曲率を変化させる。基本的な考え方の理解のためには有益と思われる。
【New】86. 最小二乗法について 3
今回最小二乗法による関数のフィッティングについて取り上げさせていただいたが、今回も前回に引き続き、更に具体的に最小二乗法の利用法について解説させて頂きたい。ここでは実際にごく普通の連立方程式を、逆関行列を用いて解き、更に最小二乗法によって解いてみることにする。
【New】85. 最小二乗法について 2
本連載53回において最小二乗方法について触れさせていただいた。少し間が空いてしまったが、今回から再びより具体的に最小二乗法の利用法について解説させて頂きたい。
【New】84. Debye積分による回折の表現 1
回折現象についてさらに勉強するためにDebye積分による回折積分計算を取り上げる。3次元的な回折強度分布の構造を考察する際などにも有益な手法である。今回は、その導出過程について解説させて頂く。
【New】83. 多数の波動による干渉、波動の合成の考え方 3
今回もまた、前回に引き続き干渉を考える上で非常に重要となる正弦波動の合成について解説させていただきたい。
【New】82. 多数の波動による干渉、波動の合成の考え方 2
本連載前々回80回において波動の合成について触れさせていただいたが、そこで多数の正弦波を合成することについて扱った。そのあたりで少し説明不足のところもあった様に思えるので、今回、少し話は戻るのであるが補足させていただきたい。
【New】81. ホイヘンスーフレネルの回折積分について 1
これまでにキルヒホッフによる、回折積分計算等には触れさせていただいた。
今回は、より回折理論を直感的に表すホイヘンスーフレネルの回折の考え方について、改めて整理させていただきたい。ここでは主に参考文献1)を参考にさせていただいている。
牛山善太 光学“深掘り”トピックス LED照明ノーツを更新しました!
【NEW】42.レンズ、ミラーなどの曲面の表示方法2<回転対称非球面>
引き続き今回も、レンズ、或いはミラー等における、光軸に対して回転対称性のある曲面(最も一般的なのが球面)の光学設計や、製造に際しての汎用的な表示方法について解説させていただく。前回では球面、放物面、楕円面、双曲面について考えたが、ここではさらに複雑な形状の回転対称面について触れる。
・・・・・・・・・
続き・本文はこちら